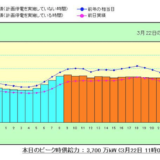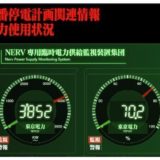(読了時間=約 2 分)
昨日、中央制御室の照明が点灯した3号機だが、公開された写真を見たとこと本当に照明が点灯しただけで、計器類への通電はまだのようだ。真水を送るポンプの試運転を実施する予定だったが16:20から黒煙が出たため作業員が退避し、実現は先送りとなった。二号機の中央制御室(一号機と共用)についてはタービン建屋の放射線が高く作業が遅々として進まない。
放射線レベルは相変わらず正門前(炉から1km)は200μSV/h台で推移しているが、これは二号機での爆発後の数値上昇の影響の様に思える。これを塞ぐことが事態改善のために重要だと思う。
炉心の温度管理については、今日は一号機で炉心温度が400度を超えて(設計上限は300度)いたが、一応、対応できているようなので、残る重要課題は高い放射線レベルとなっている原因の特定と対応策実施だと思う。
(水道水)
23日午後、東京都水道局より金町浄水場での22日採取した検体からI-131が210Bq/kg検出されたとの発表があった。成人は大丈夫だが乳幼児の摂取は制限されるべき水準だとのこと。で、夕方からは都内でミネラルウォーターの買いあさりがあったと報じられた。
河野太郎(自民党の衆議院議員)さんのTweetによると、WHOの基準は10Bq/kg。国内では2000年に300Bq/kgという設定がされて、この3/19に乳幼児向けに100Bq/kgという基準が設定されたとのこと。
基準値を上回ったのは気になるが、大きなレベルではない。23日朝に採取した検体の検査結果の速報値は190Bq/kgだったそうなので、数値がどんどん上がっているわけではない。1歳未満の乳児を持つ方は気になるが、その他については実質的には問題ない水準だ。
(野菜)
野菜については出荷制限の対象品種が拡大し、さらに、摂取を控えるべきという品目まで出された。正直、一消費者としては大変わかりづらい。
イトーヨーカドーなどの大手小売や生協などは独自に商品の案税制評価を行っている。特に生協は消費者の安全のためにかなり資源を割いており、。チェルノブイリ事故の際に購入した機材を使って毎日数品目独自に放射性物質のチェックを行っているそうだ。一般消費者は個別商品で思い悩むより、調達先のチェック体制で選別してゆくのが現実解かもしれない。
環境への影響は気になるが、ヨウ素131は半減期が短いのであまり問題にはならない。一年間継続して摂取した場合、とも言われるが、現状の放射能漏れが止まればこれはじきに消えるので現実的な前提とは言えない。チェルノブイリ事故では事後の環境汚染で深刻なのはセシウム137などの半減期の長い元素で、この濃度に注目しないといけない。
この影響がどの程度なのかという分析はまだ見えない。文部科学省は緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI:スピーディ※)というものを持っており、23日夜になってようやく分析データが一部開示された。この辺りについては早急に詳しい分析が必要だと思う。文科省だけに閉じず、いろいろな知見を集めて議論すべきだ。