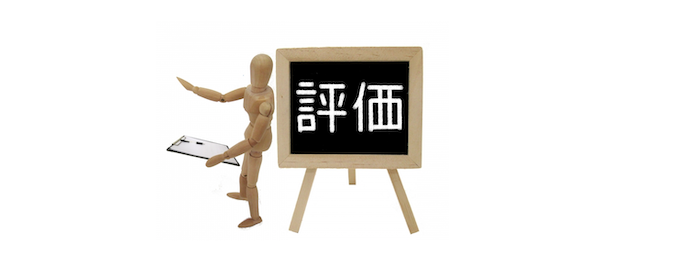(読了時間=約 3 分)
能力評価の話が途中だったので続きの話を。。。
コンサルティング会社では全員が少なくとも年に1回評価される。ファームによって若干違いはあるようだけど、うちの場合は360度評価なので、上司も部下も同僚も、一緒に働いた人全員が評価対象になっている人についてコメントしなければならない。
評価にあたっては、先に紹介した様な評価基準に沿って、その見解が導かれた具体的事実を交えながら説明していかなければならない。およそ人の評価話というのは「まだまだ未熟でもう一皮むけて欲しい」とか「前の仕事のノリでやってるだけでまだ馴染んでない」とか、ざっくりとまとめて話したくなってしまうものだけど、それだけで終わるのは許されない。必ず評価基準ごとのパフォーマンスに分解して話さなくてはならない。
しかも証拠も出さなくてはいけない。証拠というのはつまり、評価の根拠となったファクトだ。こういう状況で、こういうことになったから、○○と思うんです、という感じで話す必要がある。これは、慣れるまでは結構大変だ。
でも、数年も在籍すればすぐに慣れる。何しろ360度評価だから働いた全ての人についてコメントをしていかなくてはならない。年間で平均でも4-5人。多い人は10人以上なんてこともある。すぐに経験値が上がってくるわけだ。だから、役職レベルに関わらず、ある程度の在籍年数の人の間では、評価基準に関わる一定レベルの共通理解や熟練度が形成される。これは360度評価の良い面の一つだと思う。
***
上の役職になってくると、自らが評価者として若手メンバーの評価を行うことが求められる。この評価能力というのも、同様に経験値をもって一定水準まで底上げされてゆく。
例えば、人間のパフォーマンスというのはいろんな要素が有機的に絡んで発現する。例えば、アウトプットが出てこないといっても、本人のアタマの中には優れたアイデアがあるのにコミュニケーションがヘタなの伝わらない、という場合もあれば、アタマの中に何も無いこともある。いろいろな状況でのパフォーマンスを見ながら、何が真の問題かを解明していかなくてはならない。
また、人間である以上「相性」というのもある。お客さんとか、特定の状況・テーマとか、特定のマネージャーとか。相性に左右されないというのも能力のうちだが、またま相性が悪かった事例を以てその人の能力だとするのは適切ではない。評価としてアンフェアだし、成長のための課題が導き出せない。
評価にあたってはいろんなコメントが出るが、それをそのまま間に受けるのも好ましくない。人間なので、内心嫌いな人の評価にはバイアスが入ってしまうこともある。あるいは、コメントを述べている人がまだ評価に不慣れで、ちゃんと能力評価ができていない場合もある。そういった場合にはコメントに含まれるバイアスを補正して解釈することが大事だ。
こういったことを加味しながら、評価対象者の評価を行う。そして、本人が抱えている課題と解決すべき問題の所在を明らかにし、成長のために何をすべきかという解決策を検討する。良い・悪いの評価よりもその後の方が分量が多い。
さらに、それを全員で議論する。評価者ごとのばらつきをなくし、評価者だけでは見えてなかった問題や解決策のアイデアを出すのがその目的だ。これを各人ごとにやっていくので、毎年5日程度人事評価会議に費やされることになる。
***
これが各人年一回経験する評価なのだが、実はPDCAサイクルはこれだけではない。
メンバーは特定の仕事(プロジェクトとか、ケースとか呼ばれる)にアサインされるが、その開始段階でマネージャーとそのプロジェクトを通してどう成長するかを話し合う。マネージャーはそれに基づいて、プロジェクト期間中に割り当てる仕事の内容や難易度を調整するわけだ。そして、プロジェクトが終わると、フィードバックを行う。年間の人事評価のミニチェア版みたいなものだ。
さらに、プロジェクト期間内でも、マネージャーは日々のやりとりを通してメンバーを評価し続けている。だいたいメンバーの能力の110-120%程度の仕事を与えるのが良いマネージャーとされる。そのままじゃできないが、背伸びすれば何とかなるという水準で、この背伸びが成長につながるわけだ。
さらに、メンバーが悩んでいれば、ちょっとしたヒントとか、ガイダンスとか、仕事のコツとかを教えてあげる。こういうことで壁を乗り越えさせようとするわけだ。精神論も時には必要だけれども、具体的なガイドを与えるというのは非常に重要だし、効果が現れやすいので多用される。
日々のやりとりの中で、当初計画したような成長が実現できていなければ、仕事の振り方を変えてゆく。パフォーマンスが極度に悪い時は、プロジェクト終了を待たずにフィードバックセッションを持つこともある。この辺は状況に応じてフレキシブルに対応するのが常だ。
実際、マネージャーとして仕事をしていると、本業である問題解決と、メンバーの評価・育成とが50:50程度のマインドシェアだと感じるくらいなのである。
***
外資系で「アップ・オア・アウト」というと、次々と無理難題ふっかけられて孤軍奮闘し、うまく成果をあげられないと年度末の評価で「君、もうクビだよ」と非情に宣告されるようなイメージを持つ人がいるかもしれないが、それは大きな誤解だ。
上に書いた様に膨大な労力が払われ、能力の現状と課題が徹底的に分析され、壁を破るためのあらゆるアイデアが議論される。実際に働いてみれば、異常なほど細かい能力分析と、それに基づく膨大なフィードバックが与えられることに気づくだろう。
平均勤続年数自体が一般のベンチャーと比較しても変わらない話をしたが、実際、辞める要因を見てみても、アウトの宣告を受けて辞める人間はむしろ少数派だ。大半は、自分なりのポジティブな理由であったり、おびただしいフィードバックの中で自分の目指すものとの違いを感じて他に行く。アウトの宣告を受ける者でも、敢えて宣告を受けるまで頑張ってみようという確信犯もいる。皆が想像するような形で会社を去る人間は極めて少数派だ。
勿論人間のすることだから100%とは言えない。私が在籍した期間の中でも評価の体制や精度は随分向上したと思うが、逆に言うと、それだけ改善の余地が大きかったということでもある。
それでも、入った人の成長に向けて最大限の努力をしているという点は胸を張って言える。そこまでの想いと労力をつかっているのが「アップ・オア・アウト」というポリシーだ。少なくともうちの会社はそうだし、自分が聞く限りは、コンサルティング業界はどこも同様だと思う。