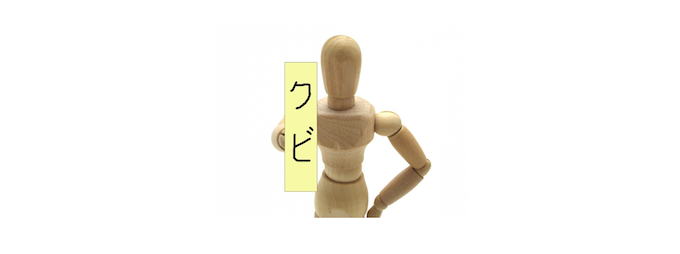(読了時間=約 2 分)
外資系でよくありがちなのだが、うちの会社も所謂「Up or Out」ポリシーというものを採用している。簡単に言うと、一定の年限内で昇進できなければ辞めなければならない、ということだ。
マネージャーとか、アソシエイトとかいろいろ会社ごとに呼び名があるが、こういった役職名に相当するのが cohort というもの。上の cohortに上がるのを promotion と言うが、ある一定のJudgeが入ることになる。それなりに要件を満たさなければ上には行けない。
また、同じ cohort の中もいくつかの level に分けられている。cohort を上がるのは何年かに一度だが、level は皆等しく毎年上に行かなければならない。昨年と同じ level に留まるということは原則あり得ない。
だから、cohort を構成する level の数が、次の昇進までに与えられた年数ということになる。
日本の大企業からこの業界に入る人にとっては結構インパクトがあるルールだと思う。これに恐怖するのは中途採用だけかと思ったら、新卒でも結構気にはしているらしい。先日話しをした新卒がそんなことを言っていた。
でも、10年以上この業界にいる経験から言えば、最初に感じる印象ほど厳しいものではなかった。
コンサルティング業界の平均勤続年数は3~5年程度と言われている。
一見、短いようにも思えるが、例えば日本のベンチャー企業の平均勤続年数も大体同じくらいだったりする。
しっかりした統計は手元にないが、以前、証券会社でIPOを担当していた経験から言うと、公開予定の会社で平均勤続年数が3年台というのは珍しいことではなかった。3年を切ってくると、ちょっと社員の入れ替わりが激しくないですか、と審査からつつかれることになるが、3年を超えていればそう問題にならない。さらに平均が5年を超えてくると「結構安定しているなこの会社は」という印象すら持ったりもしていた。
コンサルティング業界の平均はこれと同レベルなのだ。
確かにポリシーとして明示されると怖いものはあるが、やっていることは結構合理的だ。
基本、スタッフは毎年評価されるが、パフォーマンスが思わしくない人でもよほどひどくなければ警告で済む。半年で改善できなければ退職勧告になるわけだけれども、6ヶ月も改善のための猶予が与えられるわけだ。
ベンチャーだとこんな悠長なことはしないと思う。僕が前いた会社だと、明示的なルールはないが、「2回連続で失敗したらアホ扱いされる」というプレッシャーが強くあった。特に入社直後で失敗が続くと、「この人は駄目な人だ」というレッテルが貼られてしまって、もうボールが回ってこない。だから成果も上がらず、自然淘汰される。この辺はもう問答無用だ。
それと較べるとむしろゆるいシステムかもしれない。
逆に、明示的に「Up or Out」を掲げているために、それを埋め合わせるかのように「人を育てる」仕組みに注力するような面もある。
「この人には早く辞めてもらわないと、新しい人が入ってくるスペースが作れない」
という言葉を聞いてドン引きしたこともあるけれども、
「本人の人生のためにも、早めに結論を出してあげたほうがいい」
なんて発言を聴くと、それなりの理があるようにも感じる。
実際、優秀な人を獲得できる確率はそう高くはないので、獲得した人を育てる方向に力を向けざるを得ない面もあるのだ。だから、厳しいポリシーを掲げる一方で、人を育てることをきっちり考えることも行っている。そして、どうやって改善可能な領域を特定し、その改善ポテンシャルを具現化するかというところに、相応のノウハウも形成されている。
Up or Out というのは、そういう側面をも併せもつ生態系なのだと思う。
ということで、明日以降少しこの辺の話をご紹介します。