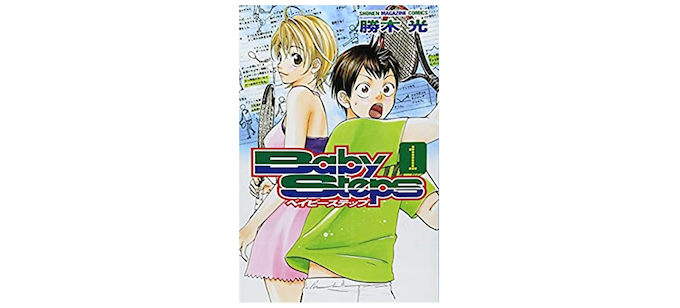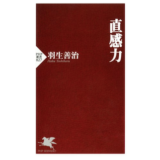(読了時間=約 2 分)
週刊少年マガジン連載中の「ベイビーステップ」がPDCAマンガだという話。
このマンガはテニスを題材にしたスポーツ物で、高校生の主人公がテニスに出会い、練習をしてどんどん強くなって試合で勝ち上がるというストーリー。これだけを見ると、よくある少年マンガの一つでしかない。
変わっているのは、主人公が極度に几帳面な性格の優等生で、自分のやった試合や練習の全ての球の軌道など、あらゆることをノートに記録するという奇怪な性癖があるということ。試合会場でもゲームが終わって休憩になるたびにノートにカリカリ書込み、皆に異様がられる描写が何度も出てくる。
ところがこれが馬鹿にならなくて、彼はこうした豊富なフィールドデータを分析することで、相手に勝つための戦略を構築し、最後には勝利を手中にしてゆく。
この過程が、綺麗にPDCAサイクルになっているのだ。
- 試合前の「予習」で試合に勝つための戦略を立てる - Plan
- 試合開始後は事前に立てた戦略に従ってプレイ - Do
- ゲーム後の休憩中に問題点を抽出し - Check
- 過去の対戦データなども交えて原因を分析 - Analyze
- 休憩終了してまでに、戦略修正の仮説を構築 - Plan
この繰り返しで最後は対戦相手を凌駕してゆく。
面白いのは、短期間で問題解決をしてゆくための実践的なPDCAの回し方の示唆が見られるところ。
第一は、全体観を固めてからディテールに入ってゆくこと。
対戦相手の成長が著しくて戦略の見直しが必要になったときなど、主人公はまず、相手のサーブへの対応とか、効果ありそうな攻めのパターンなどといった重要なポイントに絞って目処をつける。ゲームが終わったところで主人公が「よし、これで大まかな方向性は明確になってきた」なんて言ったりする。
実際の問題解決の現場でも、大小様々な問題が出てくることが多い。何も考えずに端から順番に取り組んで行くと解決できる課題の数は増えるかもしれないが、いつまでたっても全体像が見えないことになる。それよりもまず重要な問題に的を絞って解決策の全体像の骨格を明らかにする方が効果的だ。
第二は、大きなPDCAの中で小さいPDCAを何回も回すこと
主人公は、全体的な戦略をゲーム終了ごとに組み立てて検証する一方で、サーブの打ち方とかリターンの返し方といった個別の施策についてはワンプレーごとに振り返り、改善を加えてゆく。このあたりの問題の切り分け方と、PDCAの機会の生かし方がなかなか秀逸。
ワンプレーごとに振り返ることで、戦略の手応えも評価できる。仮に相手からポイントがとれなくても「だんだん良くなってる」「このまま行けば逆転できる」なんて言葉が主人公の口から出るが、これがすごくリアルだ。
第三は、必要に応じて定量化指標を作り、分析を深めてゆくこと
主人公は、相手のコートを10×10のマス目に分け、練習によってそのマスを狙って打てるだけの精度を獲得する。ところが実戦で使ってみると、コントロールショットは球速が遅くなるので相手に追いつかれてしまう。相手に追いつかれないように強く打つと、今度は精度が落ちてしまう。
ジレンマに直面した彼は、球のスピードと精度の最適バランスを探り始める。10×10の精度で打つためには60%の力だった。100%で打つと6×6マスの精度になってしまう。では、80%の力で8×8の精度で打ったらどうだろう。という形。
ポイントは、スピードと精度という二つの変数をきっちり定量化して両者の関係式を明らかにしていることだ。これによって最適値を見つけ出す検討のフレームワークが形成される。
それに仮説の立て方も筋が良い。10×10のコントロールショットで打った後、6×6のパワーショットを打って失敗し、では、その中間では、という形で探って行っている。コントロールにこだわる余り、徐々に精度を下げて、ということをやっていたら短い時間で最適値を見つけ出すことはできなかったかもしれない。
ネットでこのマンガの書評をいくつか読んでみたが、PDCAマンガだという評価は見当たらなかった。また、掲載誌での紹介文を見ていてもPDCA色を特徴として打ち出しているようには見えない。それなのにどうしてここまで濃ゆいのかが実に不思議だ。
単行本も出てますが、雑誌に連載中なので、興味を持って貰えたらまずは買うか立ち読みするかをしてみると良いと思います。