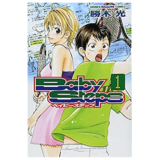(読了時間=約 2 分)
前回に引き続きコンサルティングテクニック的な話。
仮説思考というのも昔と比べるとよく耳にするようになってきていますが、この「仮説」という言葉も少し誤解されて使われることが多いように思います。
先日、若手のコンサルタントにある中途入社したコンサルタントの話を聞く機会がありました。結論から言うと評価は非常に高かったのですが、その理由が
「○○さんの仮説はよく当たるんです」
占い師かよ・・
思わず心の中でツッコミを入れてしまいました。
でも、こういう考え方は意外に珍しくありません。
答えを想定し、それを一旦仮説と呼んで、ちゃんと事実で検証する。それが検証されなければ別の「答えの可能性」を上げて検証を行う。こういう検討プロセスを行う場合、最初の仮説で答えを当てられる能力は、検討の手戻りをなくすことになりますので、非常に高い評価を得られることになります。
でもこれ、実は大きな落とし穴があります。
一つは、ありきたりの答えしか得られず、本当に難しい問題を解決するブレイクスルーが得られないこと。
そして、「仮説が当たっいて欲しい」というバイアスが働くので、検証のための分析やロジックが歪むことがあることです。
先の例でも、よく調べてみるとその先輩コンサルタントに業界経験があり、そのためにカンが働いた、ということでした。結果として検討を効率的に進めることができたのは事実でしょうが、それは問題解決能力とは少し違います。その業界に長年いる人でも悩んでしまうような難題に当たったとき、彼は”当たる”仮説を提示できるのでしょうか?多分、難しいと思います。
難しい問題でもちゃんと仮説思考を機能させるためには、仮説の正しい使い方を知っておく必要があります。
私は、仮説の目的は「問題を検討を前に進めるため」だと教わりました。それが正しいかどうかは問題ではありません。敢えて極端な仮説を掲げることで検討が進むこともあります。
「仮説」でなくて「仮設」と書けとも言われました。工事現場の仮設工事のようなものだというのです。
例えば、業界全社利益が出ないような激しい価格競争が起こっている場合、じゃぁ「それが未来永劫続くか」と言えば、Noでしょう。何らかの落ち着きどころがあるわけで、じゃぁそれは何なんだという話になる。そこで生き残るためには何をすべきか、という議論も見えてくる。
価格競争に対応するための対処策の候補をいくら上げても対症療法にしかなりません。本質的な問題を暴き出すために、敢えて極端な仮説を上げて議論を進めることも時として必要なわけです。
難しい問題があったら、なぜ解決できない要因を考えてみて、もしそれがスッキリ解決できたら万事OKかを考えてみてもいい。
例えば、技術が劣るので市場シェアを獲得できないという人がいたら、「もし技術力が競争相手と同水準だったらシェアはとれるか?」と考えてみる。どうやって技術力を上げるかの話は一旦横に置いておくのがポイントです。そんな無責任なって?いいんです、「仮設」なんですから。
もし仮に技術力が改善できたとして、それで問題が解決できるんだったら、技術力が問題の本質です。そうなったら、次に技術をどう底上げするかを考えればいい。
でも、それでも問題が解決しない場合、つまり「技術が改善しても販売力がないと・・」という話だったら、技術力改善は本質解ではないわけです。技術力改善云々を考えるよりもっと大事なことがある、あるいはもっと根本的なところを変えていかないとムリということになります。
答えがどうあれ、仮設を置くことで検討対象の幅が狭まるというのが分かっていただけると思います。
答えを当てようとしていると、なかなかこうできません。技術を改善できそうな目算がたたないと「技術が改善できたら」という仮設を提示するのを躊躇するからです。結果、技術力改善が問題の本質かどうかわからないまま悶々とすることになります。
直感で答えがわかるうちはそれで進めるのも良いでしょう。効率的ですから。
でも、それで限界を感じた時には、「仮設的な」仮説の使い方を試してみるとブレイクスルーが得られるかもしれません。