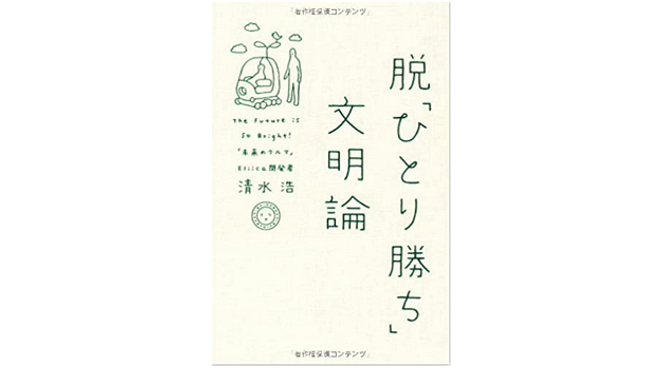(読了時間=約 3 分)
昼間、電気自動車(EV)についてのTweetにコメントしたついでに、ここでちょっと詳しく書きます。自動車業界は専門外なので、ごくごく初歩的な知識に基づく個人的見解です。
まず最初に理解すべきなのは、電気自動車(EV)は従来の自動車とは全く異なるということです。
部品点数は従来型の自動車の半分から1/3です。
エンジンがなくなると、補機類(ラジエーター、スターター、エアクリーナーなどの吸気系、エギゾーストや触媒などの排気系、点火系)もいらないし、トランスミッションやデファレンシャルギアなどの駆動系も大幅に簡略化されるのだから当然ですね。
設計の基本原則も大きく変わります。
エンジンの発する熱や振動への対策は基本いらなくなるし、燃料や油圧系の配管や動力の物理的な伝達も考える必要が減るので設計の自由度が広がる。車輪の中にモーターを仕込んで、床面に電池と制御系部品を配置して車台を作り、その上に乗用車やトラック、バスなどの用途に応じた「ガワ」を載せるという発想すらあるのです。
この結果、産業構造そのものも大きく変わることになります。
自動車産業はTier 1, Tier 2 などと呼ばれる多層構造のサプライヤー群を抱えていて全体で一大産業を形成しているわけですが、上述の通り部品点数が大幅に減るのでこの構造が大きく簡略化されます。
また、パーツ同士の「すり合わせ」の必要性が少なくなって各製品がモジュール化し易くなるので、垂直統合型でないモデルも成立することになります。つまり、電機業界の様な水平分業型のプレイヤーが台頭してくる可能性があるわけです。
さらに、技術者の人材も大きく変わるでしょう。内燃機関に関連する従来型の技術・ノウハウの価値は下がり、新しい設計思想で従来の自動車の枠を壊す斬新さが競争力を有む時代になる。特に、今まで技術のコアを支えていたエンジン技術者たちには厳しい時代になるかもしれません。
既存の自動車メーカーはこのような破壊的変化に対して前向きになれるはずがありません。
だから、環境問題への解答としては、HEV(ハイブリッド車)を最終解にしようとする。HEVはエンジンを使うため設計思想的には従来の延長線上にあり、産業構造を壊さないからです。
EVは問題点も多いので普及は難しいという話もありますが、インフラ(電気スタンド)や技術的課題(充電時間や航続距離)などは、生産数が増えて投資が十分なされればいずれ解決できる問題です。
自動車業界の人がこの主張をするのは、少しバイアスがかかっているのではないかと思ってしまいます。EVは難しいという話になって投資が抑制されれば技術的発展が滞り、予想通りEVへの移行は遠い未来になってしまうわけですから。
確かに、既存の自動車メーカーが皆そう動いてしまうと、事実として、EVへの移行は実現しないかもしれません。
でも、これにはいくつかの撹乱要因があります。
第一は、自動車業界の合従連衡にあぶれたメーカーによるEVへの踏み込み。
環境対応などへの開発投資などの影響もあって自動車業界は合従連衡で規模を作る動きが進んでいます。トヨタとVWは業界内でも勝ち組としての地盤を固めつつある中、淘汰されるリスクにさらされるメーカーとしては、上位メーカーに必死に追いすがるか、別の路線で一発逆転を狙うしかありません。後者の一つの手がEVというわけです。
三菱自動車がEVに注力するのはこの文脈で考えると納得感があります。同様に、経営基盤が磐石とは言えない米国の三大メーカーあたりもEVに賭ける決断をするかもしれない。そうなると生産台数規模が大きいだけに、業界の流れが変わり始めるかもしれません。
第二は、スマートシティの推進による追い風。
欧米で盛んなスマートグリッド。自然エネルギーを使った発電と配電網の高度な制御が当初の話でしたが、最近では、これが社会インフラ全体のオール電化とそれらの統合的制御といった概念まで拡大し、「スマートシティ」とか「スマートソサエティ」といった言葉で議論されるようになってきています。
現在世界各国でいろんな実証実験が進められていますが、その一つの目玉が電気自動車。地域で走る車をEV化することでCO2発生量を大幅に減らすというもの。
自動車業界から見ると充電ステーションのインフラが、とかEVの普及が、といった問題点が出ますが、こちらはインフラ屋さんの世界なので、充電ステーションは作りましょう、EVも公共交通機関やレンタカー・カーシェアリングでいきましょう、という形で解決できちゃう。
インフラ業界側としても、もともと電力だけの話だったのを「スマートシティ」という社会基盤の話に拡大するにあたり、「自動車」というのは規模感があって目を引くネタだったりするのでしょう。実証実験でEVの話が取り入れられている例が目につきます。
しかもこれ、政府から補助金が獲得できるのです。通常の競争原理を超える追い風がここにあります。米国のEV関連のベンチャーがこういったプロジェクトを狙って動いていたりしています。
今後、これらが実証実験から実行フェーズに移ると、どこかのEVベンチャーが相応の生産規模と運用実績を獲得してゆくことになるかもしれません。
div>上記二つの撹乱要因は今後数年内に具現化する可能性があります。だから、自動車業界は近い将来、大激震に襲われることになるのではないかと思うわけです。
実はここ半年、自動車業界関連の人と会って話をするたびにこの話をしています。誰も首を縦には振らないけれども、これを論破する合理的説明はまだ聞いたことがありません。
なので、素人発想ながらも結構あり得る話なんじゃないかと思っています。
今日のお勧めは、世界最速の(ポルシェより速い!)電気自動車「Eliica(エリーカ)」を作った人の著書。読むとアタマの「凝り」がほぐれてワクワクしてきます。まだだったら是非どうぞ。