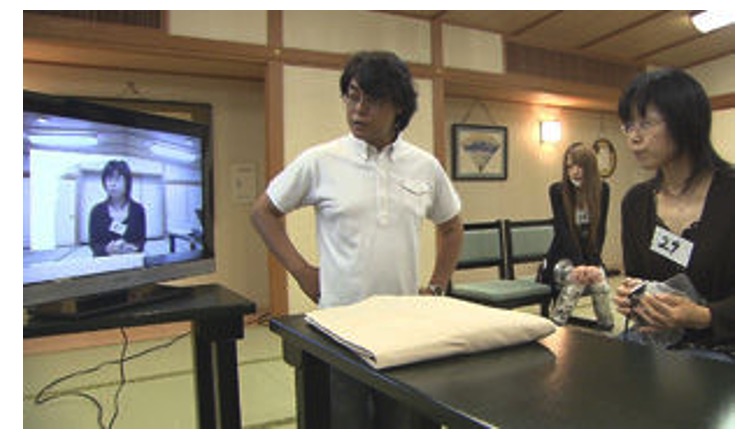(読了時間=約 2 分)
ETV特集「ネットワークで作る放射能汚染地図3」と見た。Togetterでまとめがあるので、見てなかった人は参照してみてください。
このシリーズ、最初は結構衝撃を受けたが、3回目になってくると市民運動っぽさが鼻についてあまり感情移入できなくなってきた。やっていることは正しいと思うけれども、自分の中でこの問題意識は既にもう持っているので、関心はそれをどう解決するかというとことに移ってきているためだ。
一軒一軒居住者を訪ねて回り、8時間もかけて除染をしましたというのは素晴らしい行為だが、こんなやり方をしていては被災している人たち全員を救うのに何年もかかる。しかも、今回の除染で放射線レベルが下がったとはいえまだ高い水準。果たして「解決」をなし得るのかという絶望感さえ覚えた。

そもそもの問題として、少し細かすぎる議論に入っているのではないかという印象もある。
「前例」であるチェルノブイリと比較してみると、福島原発の汚染は汚染度やその広がりの面でかなり小さい。その一方で、健康被害や現状回復のために求める水準はかなり高いものとなっている。
「チェルノブイリ原発事故と福島原発事故の比較に関して」という記事によれば
- 強制避難の対象になったのは原発から30km以内の地域のみ
- 国内で最近話題になる「1平方メートル当たり55万ベクレル」という水準はチェルノブイリのケースでは強制避難対象ではなく「移住(第二次移住)」区域とされた地域。しかも結局移住は進まず、20万人の人がいまだ居住中
- チェルノブイリでは10Gy(10SV)の甲状腺被爆をした子供が数百人いたが、国内で3月末に行ったサーベイでは50mSV以上の被爆をした子供は事実上いなかった
ということで、大分受ける印象が異なってくる。
ここで引用されている「京大の今中准教授の研究」も併せて読むと、チェルノブイリのケースでも許容できる被爆量としては年間1mSVということにはなっていたようだ。ただ、あくまでもこれは目指すべきターゲットであり、ここを超えたら絶対駄目、というものにはなっていない。
日本の世論、特に反原発市民運動家の人たちの論調では、ここが非常に硬直的な印象がある。理想を掲げるのは大事だが、一方でそのための社会的コストも考えなければ現実的な解は得られない。今の日本はそれを考える段階に入ってきていると思う。

政府は着実に「現実解」に向けて歩を進めつつある。昨日は文科省が土壌のセシウム濃度マップを公開した(上図)。汚染地域の除染については、国直轄で行う旨の法案が8/21に提出されている。今のところ警戒区域の除染は政府が行う方針の様だ。また、民間の事業者が除染を効率よく行う技術・手法を開発しつつあり、それを活用したモデル事業も行ってゆくようだ。
8/27の福島復興再生協議会での管首相の発言は注目に値するものだった。一つは、汚染のひどい地域においては今後20年は戻れない可能性もあるということ、もう一つは、福島に中間貯蔵施設を作りたいというものだ。除染を大規模に行ってゆくとなれば、それに伴い発生する放射性汚染物質を貯蔵する場所の確保も重要になる。地域住民側の反発は当然あるだろうが、こうした厳しい現実を議題に上げることは、前に進むためには大事なことだと思う。
***
「土壌のセシウム濃度マップ」は、ETV特集のこのシリーズ最初で科学者たちがボランティアで作っていたものと同様のものだ。政府は初動では確かに遅れていたけれども、その後体制を整えて同様の調査をきっちりまとめ、除染に向けたステップに動きつつある。もちろんいろんな問題は引き続きあるだろうが、全体としてより沢山の地域が改善に向けて動き出すことは間違いないだろう。
こういう動きを考えると、ETV特集のあの映像は、人の行いとしては素晴らしいのは事実だけれども、いかにも情緒的で、アマチュア臭く感じてしまう。ということで、今回はいまひとつ感情移入できなかった。