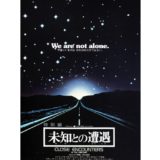(読了時間=約 2 分)
最近、細野氏が注目されてるみたいだ。メディア対応で非常に率直に原発問題に対して発言する姿勢が評価されているらしい。
細野豪志氏に注目 http://news.livedoor.com/article/detail/5732780/
発言している映像は見ていないが、記事などを見る限りかなり率直に政府の問題点も語っており、好感が持てる。枝野さんは当初評価は高かったけれども、パニック抑制のためにとったスタンスちょっとね。元弁護士ということでソツがないのは確かだけれども、人の信頼を得るのはそれとは違うメカニズムが働くようで。
福島原発事故は非常に残念だが、同時に日本にとって、いや、人類にとって数多の教訓が得られる貴重な機会でもある。徹底した原因究明と、事後対策や影響評価のモデル化を突き詰めて、今後のスタンダードをしっかり提言してゆくべきだと思う。
国内では脱原発の議論が出たりしているが、日本だけがやめても問題は解決しない。世界で原発推進を継続する国はあるし、そもそも隣国の中国では多くの原発が稼動している。そして、事故は必ず起こる。これは確率的な問題でしかない。その時にどうするべきか、その教訓を得る機会が今ここにあるわけだ。
中国については先日、高速鉄道が約40名もの死者を出す事故を起こした上、事故車両を土に埋めて一日半で営業再開したやり方に批判が集まった。
ただ、この批判は先進国のメンタリティだとも言える。実際、批判はあるものの、再開した列車にはちゃんと乗客が乗っている。需要はあるのだ。リスクは承知で、利便性をとる人たちが明らかに存在する。いかに他国から見て異様に見えようとも、少なくとも中国内においては一定の理があるわけだ。
鉄道技術の輸出には大きな影響があると言うかもしれない。確かに今回の事故は列車運行システムの問題である可能性が高く、このような状況ではいかに車両の性能が良くても危険であることにはかわりがない。でも、中国が今後鉄道技術を売り込む先は欧米や日本ではなく、新興国だろう。彼らのメンタリティは先進国のそれとは若干異なるかもしれない。
それに、運営実績が増えればトラブルは減少してゆく。10年後には、今回の高速鉄道事故は運営初期にたまたま起こった不幸な事故だということになるかもしれない。その観点では、事故車両を保存して徹底的に原因分析する手間などかける必要はないのかもしれない。
別に中国の肩を持つわけではない。ただ、多極化が進む今の世界の中では、自らの価値基準で全てを判断すると間違いをおかすということだ。全く価値観の異なる相手と対峙していかなければならない、また、そういった相手と取引をして収益を上げていかなければならない。冷戦時代なら構図はもっと簡単だったが、今はもっと複雑になっていると思う。そして、それを踏まえて戦略を考えてゆくことが求められる時代なのだ。
先の原発事故対応についても、日本で培ったノウハウをそのまま中国政府に直接提供しなくてもいい。価値基準の違う相手に提供しても価値がわかってもらえなかったり、技術を盗まれたりで面倒なだけだ。変わりに、例えばIAEAとしっかり握って、中国で原発事故が起こった際に国際社会の圧力をしてon behalf of IAEA で日本の事故対応メソッドを導入してゆくほうが良いかもしれない。
高速鉄道事故について言えば、ドイツ・フランスに呼びかけて列車運行管理システムの国際標準を作ったら良いと思う。そもそも鉄道システムにおいて運行管理システムの価値が過小評価されているのが問題なのだ。
日本の新幹線が軽量なのは運行管理システムの設計上、衝突リスクが低く抑えられているからだ。だから車両単体で競ってもあまり意味がないのだ。日本の新幹線は台湾にも導入されたが、ここでも日本は車両管理システムを取れなかった。こういうところの問題をちゃんと認識し、手を打ってゆくべきだ。
その意味では、今回の事故は運行管理システムにスポットライトを当てる良いチャンスなのだ。そして、ドイツ・フランスと共同戦線を組む機会かもしれない。
多極化の時代では、今までの価値観を変える必要があるし、新しい対立軸でものごとを考える必要もある。そして、その発想の幅が広がると、いろいろな打ち手(仮説)が見えてくる。こういう思考は今の時代、結構重要なんじゃないかと思う。