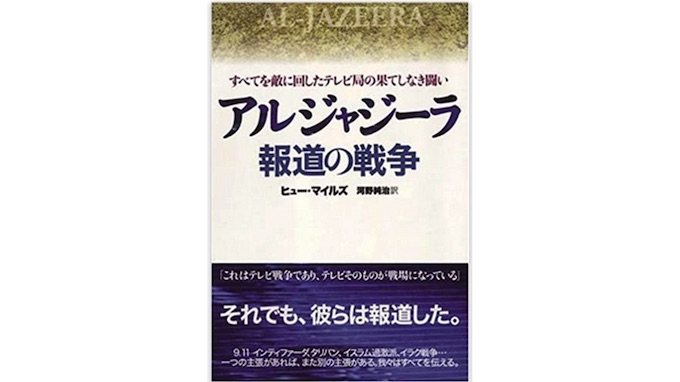(読了時間=約 2 分)
いまさらながらアルジャジーラについての本を読んだ。
アルジャジーラというのは中東(カタール)の衛星放送局で、9.11のテロの後、アルカイダのオサマ・ビンラディンの映像を放送していた放送局だ。中東を中心に活動するイギリスのフリージャーナリストが書いた本で、日本語訳もよくできているので読みやすい。2005年に刊行された本でAmazonでは中古を数百円で購入した。気まぐれで買った本だったが、なかなか面白かった。
まず感じたのは、これはベンチャービジネス的な物語だということだ。
従来中東の放送局は政府の広報機関であり、政治的・宗教的に様々なタブーが存在していた。アルジャジーラはこの中東で「公正で中立な報道」を行うことを目指して設立された。人気番組になった「反対意見」では「ヒズボラ」は反対組織か、それとも単なるテロリスト集団か」といったテーマで参加者が激論を交わした。こんな議論は国のお抱え放送局では御法度だ。視聴者はアルジャジーラの番組に驚愕し、そして釘付けになった。
もちろんこういう報道姿勢は政府の反感を買う。パレスチナ報道ではイスラエル政府が苦言を呈し、また、イスラエル政府高官へのインタビューにはアラブ各国が苦言を呈した。しかしそのような圧力にも関わらずアルジャジーラは自らの理念を貫き、視聴者の支持をどんどん拡大してゆく。そしてついに、他のアラブ各国も同様の放送局を設立しはじめる。アルジャジーラが中東の報道の歴史を変えたわけだ。さらに、いくつかの戦争報道をきっかけに、世界でCNNやBBCなどの欧米メディアに伍す存在感を確立し、舞台は中東から世界へと移ってゆく。
こういったストーリーはベンチャーの成長物語そのものだ。先日、フェイスブックの創業期の話である「facebook」を読んだが、業界や地域は違えども、路線的には同じものを感じた。
また、中東情勢に関する理解を得るのにも非常に役立つ。日本では中東に関する報道が多くないということもあるようで、基本的なことについて意外に知らないことが多い。この本では、アルジャジーラの展開を通して、1990年代後半以降に中東で起こった大きな戦争や対立について理解を深めることができる。また、中東の人々の生活や価値観などのエピソードも面白い。「反対意見」と並ぶ人気番組が「宗教と生活」なのだそうだ。これは有名なイスラム法学者がゲストとして登場し、不倫の相談から自爆テロへの疑問まで、視聴者からの様々な質問に応える番組。宗教が深く根付いているという文化が日本や欧米と比較して大きく違うし、現代の様々な事柄について宗教的解釈を与えることが新しいという点も興味深い。
さらに、この本は報道のあり方についても考えさせてくれる。放送局は政府の宣伝機関となっている国の方が数としては多いし、タリバンやイラク戦争の報道では、欧米の報道機関でも中立ではなかった。そもそも公正中立な報道というもの自体が稀有なものなのだと思う。先日の尖閣諸島関連で起こった日本国内のデモを日本の報道機関が報じないと憤る声もあるが、まぁ、世界の標準から言えば放送局なんてそんなものなのかもしれない。
構造的な問題もある。公正中立ということは、ある物事に対立する双方にとって煙たい存在だということだ。衝突を恐れていては生き残れないベンチャーならともかく、既に大きな影響力を持ち既得権益で守られている日本の放送局だと構造的に難しい面もあるだろう。これに憤っても仕様がない。ニコニコ動画みたいなところに資金と理念を持ち込んで暴れさせることを画策した方が建設的(?)な議論だという気がする。
そもそも、多極化した現在の社会においては、日本や欧米の視点でものごとを見ることですら必ずしも正しいと言えない。ただ口を開けていれば正しい情報が来るような社会を期待することは間違いだ。「一つの意見があれば、別の意見もある」というのがアルジャジーラの理念だが、自分自信がこの言葉をしっかり胸に刻み、自ら正しく物事を見ることを心がけることが大事だと思った。
ということで、この本はお奨めです。機会があれば是非読んでみてください。