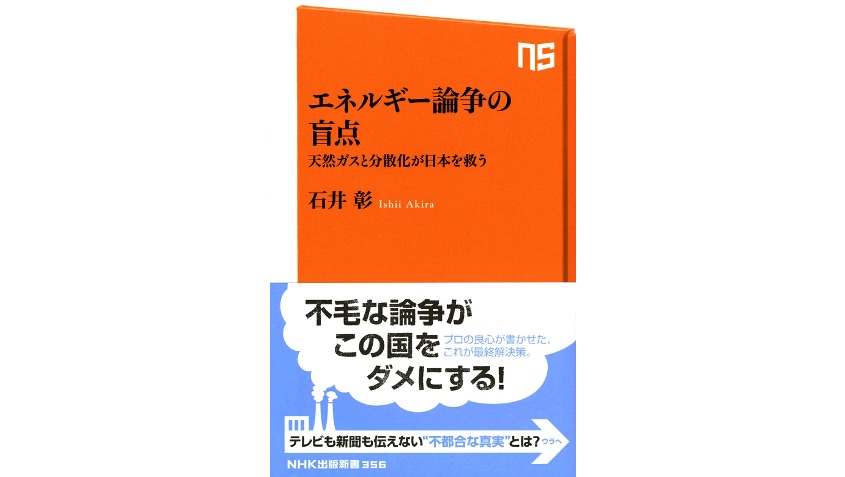(読了時間=約 2 分)
ネットで話題になっていたので購入して読んでみた。
福島原発事故以降に書かれた本で7月10日に発行されたまだ新しい本だ。
第一のポイントは、言うまでもなく昨今のエネルギー政策議論の批判と専門家の視点からの方向性の提示だ。
原発推進か再生可能エネルギー推進かという二元論への批判や、風力や太陽光発電の根本的な問題点についての指摘など、最近のネット上で目にする議論についてよくカバーされていて頭の整理になる。天然ガス発電の有望性についての指摘などはなかなか興味深い。
ネットで話題になっているのは主にこの辺りの話なので、ある意味ネタバレしてしまっていて新鮮味はないけれども、ネットの書き込みを見るだけでなく書籍として読む価値は十分にあると思う。
第二のポイントは、エネルギー産業に関わる基本観を提供してくれること
具体的には、前段の第1~第2章で、エネルギーに関わる議論のスコープとして、電気だけの議論は意味がなく、エネルギー全体として議論しなければならないといった話だとか、歴史を紐解きながらエネルギーと文明との関係を俯瞰した話などが展開される。
どんな産業でもその産業を考える上での基本的な背景や視点があり、それを知らずに他業界の常識だけで議論すると大きな間違いの元となる。特にエネルギー分野は一般のわれわれの生活感覚とな大きく乖離があるので、本書に書かれているような基本的な認識をまず理解することは重要だと思う。
第三のポイントは、「省エネ」の余地についての指摘
巷で話題になる、「家庭や事務所での省エネ」は既に取り組みが行われているし、そもそもエネルギーの総需要に対する家庭・事務所の電力需要はごく一部でしかないので、エネルギー使用全体の効率化への貢献は限定的だ。過去の歴史でも「省エネ」で最も効果の大きかったのは自動車の燃費改善だそうで、省エネ家電ではない。
資源からエネルギー消費までのend to endで考えた場合、改善余地が大きいのは発電の効率化改善のようだ。現状の発電効率は火力発電で40%弱であり、エネルギーの半分以上が廃熱として無駄に捨てられている。
福島原発事故でも、電源が喪失した中、停止後の原子炉の崩壊熱のコントロールに四苦八苦しているのをみて不思議な感じがしたものだ。何であんなに膨大な熱が発生するのに、それを使って発電ができないのかと。冷却水がどんどん沸騰して水蒸気が出ているのだからそれでタービンを回せば電気ができるんじゃないの、それでポンプ回して水を入れたら良いじゃない。でも、あまりそういう工夫はされていないのが現実のようだ。
発電ではコンバインドサイクル式のガス発電が高効率だが、これはガス発電後の廃熱でもう一つのタービンを回して電気を作っているいるからだ。コジェネレーション(熱電併給)も供給側の無駄を少なくして高効率なエネルギー供給を行うシステムだ。こういうものを拡大することで全体として、需要側の省エネ努力を上回るエネルギー効率改善が図れるという指摘には説得力がある。
***
ということで、いろいろな面で面白い本でした。
時流のネタでもあるし、新書だから2-3時間あれば読めるので、是非ご一読されることをお薦めします。