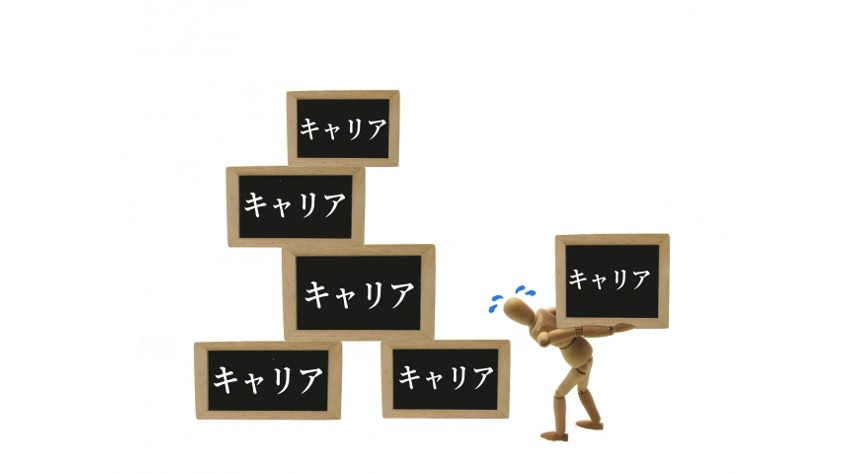(読了時間=約 2 分)
先日、struggleしているジュニアメンバーに対して送ったメールから引用。
比較的重要かつ一般的に通用する話なので、サニタイズした上でここに掲載します。
—————————————————
評価の時期ですので、チームメンバー全員と個別で時間をとる予定です。
とはいえ、いろいろ書いてくれているので先に一言コメントします。
まず、Capability developmentの話と貢献度の話は分けて考えるべきです。
前者は弱みを底上げする話ですが、後者は強みを活かすこと。
取組の仕方は全く逆です。
失点を挽回しようとしてもがいても、弱みは改善されません。
Developmentに必要なのは、自分の弱みを認め、真正面から向き合うことです。
貢献度や仕事の分担範囲は、外部環境やプロジェクト設計の問題によります。
ですので一様にはいきません。
状況により、すごく仕事が多い場合もあるしそうでない場合もあるでしょう。
それはこの業界であれば普通のことです。
仮に、状況要因によって貢献ができなかったとしても、私はその人を責めることはしません。
評価にも関係しません。評価は基本、貢献度評価ではなく能力評価ですから。
一方、プロジェクトの状況は変わっても、能力評価は同じ基準で行われます。
これは大原則。
とはいえ、指摘されているポイントが今までと全く違っていたのなら、
それは何か特殊な環境要因があったと言えるかもしれません。
しかし、同様のポイントを指摘されているのであれば、その指摘はおそらく事実です。
環境によってそれが顕在化する程度は異なるかもしれませんが、
Development areaである点には変わりありません。
具体的な評価内容についてはここでは書きません。ご自分で判断してください。
人には自分を変えられる人と、そうでない人がいます。
変えられない人は、自分の強みを活かすことしかできません。
普通の会社ならそれでも良いです。
が、この業界は、皆がどんどん昇進し、どんどん要求水準が厳しくなっていきます。
変われない人でも、強みを持っていれば最初はどんどん昇進します。
でも、その強みに要求水準が近づいてくると、急に評価が伸び悩みます。
そういう人は、そこで賞味期限が切れたかの様に輝きを失い、消えていきます。
長く生き残るのは、自分を変えられる人です。
自分を変える、変え続けるというのは、プロフェッショナルとして大成する必須条件です。
もちろんこれは大変な痛みと苦労を伴います。
でも、この業界の人は皆これに取り組んでいます。
私自身もそうですし、この会社のパートナーの誰に聞いてもYesと答えるはずです。
いずれにしても、フィードバックミーティングの時間は来週にでも設定します。
その時にまたお話ししましょう。
———————————————————–