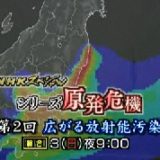(読了時間=約 2 分)
Twitterでフォローしている人の中で、自分的には「海外情報」カテゴリの人というのがいる。年明けにエジプトで発生したデモなど、海外で起こった事件について国内メディアより的確かつ迅速なツイートをしてくれていたのがきっかけでフォローするようになった。平時においても国内とは違った視点でつぶやいてくれるのでいろいろ面白い。しかし、福島原発事故に関してはこれがまったくいただけない。過度に批判的だが、ベースとなっている情報が古かったり不正確だったりで、見るに耐えない。
放射能に対する大原則は、「少なければ少ないほど良い」というものだ。一定水準以下の被爆の影響は短期的には確認されず、長期的影響は生活習慣の影響に埋没して明確には検出できない。ただ、放射能が人体に影響を与えるのは事実であり、その観点からすれば、例え明確に確認できる因果関係がなくても、被爆を最小限にするほうが「無難」というのが現状の考え方だ。そして、その考え方をそのまま適用すれば、日本は致命的な打撃を受けたことになる。通常時よりも放射能レベルが少しでも上がればアウト。しかもそれが地域全域ではなく、特定地域(ホットスポット)であっても駄目というレッテルが貼られる。大原則からすればそれは正論だけど、現実的にはアンフェアな議論だと思う。
チェルノブイリやスリーマイルと福島原発事故が決定的に違うのは、大都市圏との距離だ。確かに福島原発近傍はいわゆる「田舎」ではあるけれどもそれは日本基準での話。事故現場から半径300km以内に5,000万人を超える人が住んでいるというのは、過去なかった状況だ。直接的影響は半径30-50km圏内程度で済んだのは幸いだが、食物汚染を含めた間接的影響はより広い地域・人口が受けざるを得ない。
放射能への大原則は「少なければ少ないほど良い」であり、影響を与える閾値も不明確なので、安全基準はより保守的に設定される傾向にある。しかし、こういう事故が起こり、5,000万もの人が影響を受ける以上、「十分なマージン」を見込んだ運営というのが難しく、我々はより精緻に「安全か否か」を考えていかなければならなくなった。これが今の日本が直面しているチャレンジだ。
またこれは、人類全体にとってのチャレンジでもある。事故はいつか必ず起こる。日本が原発を廃止しても中国は原発を作り続け、いつかは事故が起こる。そして事故が起これば放射性物質が日本にまで運ばれてくる。欧州も同様だ。ドイツが原発を廃止してもフランスの原発は増え続け、そしていつかは事故が起こる。その時に我々はどうすべきか。その先行事例が今起こっていると言える。
事故の原因究明は大事だが、誰が悪いかを特定して糾弾するのが目的ではない。東京電力の体たらくはひどいし、管総理の民主党政権もひどい。でも、それはもう明らかだし、正直、これは日本の構造的問題であり、東電の現社長とか管総理が悪いとも言い切れない。スケープゴートを見つけて糾弾すれば感情的にはすっきりするかもしれないが、それはあまり意味がないことだ。重要なのは、今回のケースから何を学び、確実に起こるであろう次の事故に対して何を備えるかということだ。
放射線量測定のメッシュを細かくしたり、住民の健康状態の追跡調査はデータポイントを増やす意味では重要だろう。それにどの程度のコストがかかり、どう運営するのが最適かというのも学びになる。また、このデータを踏まえて、より現実的な許容線量限度を考えられるかもしれない。また、土壌改良などについてのコストや手間も含めた現実的解決策が出てくればそれも一種のイノベーションだ。
ぐちゃぐちゃ内輪もめしてないで、日本が一体となりこの問題に向き合い。得たノウハウをしっかり世界にアピールしてゆけばいいのにと思う。そして、原発推進を進め、原発業界でのリーダー奪取を狙うフランス政府とアレバ社にはそのノウハウを高く売りつければいい。
原発事故はそういう捉え方をするべきものだと思う。