(読了時間=約 2 分)
コンサルティング会社では、若手を鍛えるためにメモを書かせることがある。ミーティングメモとか、インタビューメモだ。下っ端の仕事という受け止められ方をされやすいが、これは実際、基礎力を鍛えるのに良い訓練になるのだ。
大体当日の夜中までにはメモが上がってくるが、最初はダメダメなことが多い。
まず、情報量が少ない。話した内容が全然キャプチャーされていない。あるいは、自分かってな解釈で文脈が歪んでいたりすることもある。こういうのは論外なのでまず突き返す。
で、次の段階に位置づけられるのは、相応に情報量があるが、まとまりがないというもの。ここからがコンサルタントとして成長するためのポイントになってくる。
***
経験のあるコンサルタントが書くメモは、すごく構造化されている。論点にキッチリ分かれていて、その論点がより大きな論点と関連づけられ、全体としてピラミッド的な構造を形成している。詳細情報を網羅していながら一覧性があり、結論を一言で言えば何かということまで容易に理解することができる。
クライアントに提出できるレベルの資料のことを client ready と言うけれども、インタビューをとりながらとったメモがそのまま client ready なものになっている人もいる。要は話を聞きながら、全てを構造化してきっちり理解しているということだ。
***
これは、コンサルタントとしては必須の基本技術だ。だから若手コンサルタントにも当然ながら要求してゆくことになる。でも、これがなかなかできない。
最初は大体筆記録のような形になることが多い。ドットポイントを使ったりして見た目はそれっぽく見せる人もいるが、大項目と少項目との間の関係性が曖昧なので、ロジックツリー的なものにはなっていない。単に、聞き取った言葉を並べただけに過ぎない。ただ、これでも情報がちゃんと網羅されているのであれば最低限機能はできる。
少し慣れてくると、「段落」をつけられるようになる。その時の話のテーマを表題としてつけ、テーマが変わるまでをひとまとまりにして書く。見た目はあまり変わらないが、発展段階としては重要な一歩だ。
もうちょっと慣れてくると、段落の中のサブ項目が明示的に記載されるようになる。あるテーマについて3つの視点から話がされているとすれば、テーマが段落名、3つの視点がサブ項目になる。このサブ項目を突き詰めていくと論点になってくる。
論点まで抽出できてくると、かなり構造的には見やすくなってくる。論点について、その人がどういう意見を言っているのかが示され、その根拠が論点のサブ項目として記載される。会議などであれば、賛成、反対意見それぞれについて、その根拠が整理される。
ここまで来るとコンサルタントのメモとしてはほぼ完成だ。あとはそれぞれの論点の間の構造をツリー状に整理していけば、構造的に整ったメモが完成することになる。
***
この進化はそれなりに時間はかかる。自分の経験で言えば、毎日メモをとっていて約3ヶ月程度かかった。経験あるコンサルタントがファシリテートする会議のメモであり、会議進行自体が混乱していなかったのでやりやすかった面もある。通常ならもうちょっとかかるかもしれない。
メモをとりながら論点を抽出できるくらいまでになってくると、会議やインタビューで「脇道にそれた発言」が出るとストレスを感じるようになる。
人によっては、AはBであるということを主張しながら、根拠を挙げていくうちにAはBではないという事例が出てきて挙句の果てに、だからこの問題は難しい、などと締めくくったりする。こういうのはかなり辛い。
たぶん、論点思考というのは人間の自然な思考ではないんだと思う。
人間というのはもっと感情的であり、直感的な生き物であって、論理的な生き物ではないのだろう。勿論訓練すれば論理思考ができるようになるのは事実だろうが、それは明らかに訓練が必要な技能なのだ。
その訓練をするために、今日も若手コンサルタントはメモを書き、マネージャーから怒られるのである。
Logic and Format の参考書として必ず名前が出てくる名著。コンサルの基本を学ぶのに必須の本です。この業界に入ってくる人で「一回読みました」とか言ってケロっとしている人がいるが、それじゃ全然足りない。基本というのは身につけるまで一万回くらい反復練習するものであって、その間、本書のような本は常に横に置いておいて読み直さなければならない。人間の自然な思考ではない方法論を身につけることの地獄を知り、それを乗り越えるまで、本棚に戻してはいけません。
あ、コンサルタントになりたい人への話です。。
普通の人は斜め読みで十分です☆

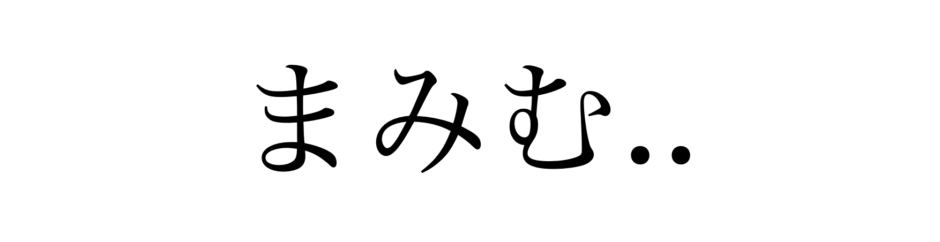


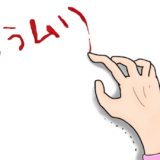
こういうためになるエントリーはたくさんの人が読むべきなので、
是非ツイッターに投稿できるボタンを設置してください!