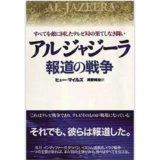(読了時間=約 2 分)
コンサルティング業界というのは忙しい業界と言われていて、就職面接をしていて直接聞いてくる学生もいるし、既に腹をくくって面接に来る人もいたりする。ネットや書籍で経験者が話をすることもあるが、その一方で、そんなに働けるわけがない、とか、別の業界の方がもっと働いている、といったコメントも見かける。議論が錯綜する原因の一つは、話の内容がやや大雑把になっていることだ。当然ながら忙しい時期もあればそうでない時期もあるわけで、その構成比の問題もある。それらを一括りに議論するのは正確ではない。
そこで、今回は正確なデータを使って事実関係を検証してみたいと思う。ちょうどこの業界に入ってしばらくした頃、私は毎日その日に仕事をした時間を手帳に記録していた。出張は殆どなかったので、移動時間が入っていたとしても都内のタクシー移動程度だ。通勤時間は含まれていない。昼食は殆ど自席で弁当であり、その間もPC画面や資料を見ながらなので、仕事時間に参入している。また、休日に家で資料を読んだりスライドを書いたりした時間も参入している。2001年初から2004年末までの4年間にわたる記録を週単位で集計したのが下のグラフだ。

正確なデータを比較したわけではないが、私は会社の中ではハードワーカーだという評価を戴いていた。実績面でもまずまず順調だった(今まで生き残っているのが証拠)。また、この4年間で大きく体調を崩すことはなかった。時々疲れたり風邪を引いたりはあったけれども、基本的には元気に毎週働いていた。なので、上の労働時間は、この業界としてはある程度平均的かつ持続可能なものであると言えると思う。
4年間のうち、年末年始や夏季休暇を除いた週平均労働時間は66時間。1ヶ月を4週間とすると残業104時間ペースだ。前半2年の方が比較的労働時間が多いが、それでも週70時間台であり、週80時間を越えることはあまりない。証券会社勤務時代は忙しい時期で月の残業が100時間程度だったと記憶しているので、月100時間残業が「平均値」だということは確かに忙しい業界なのかもしれない。でも、そんなに極端に忙しいわけでもない。この程度の平均値で働いている人は他の業界にもたくさんいるだろう。
でも、忙しい時期もある。コンサルティングの仕事は、プロジェクト(会社によってはケースとも言う)という単位で回っている。なので、忙しいプロジェクトに入ると急に労働時間が跳ね上がるわけだ。4週間の移動平均をとっていくと、2004年5月が最高値で、4週間の平均で週94時間(残業216時間)だった。この時は流石に疲労困憊していて、トイレで便座に座ったまま気づかぬうちに寝てしまったこともあった。この業界に勤めていると、こういう状況に陥ることもある。
ちなみに、忙しいことの代名詞として「徹夜」というのがあるが、徹夜をすると翌日以降疲労が残ってしまい、疲労感の割に長時間働けてないことが多い。安定して長時間働くためには、毎日規則正しく働くことが効果的だ。例えば、平日は毎日10時から24時まで働き、土曜日は20時くらいで切り上げて呑みに行く。そして日曜は一日寝て過ごす。これで週80時間。こうすれば、徹夜するよりも疲労感がはるかに少ない。これは、データ分析と試行錯誤によって導き出した結論である。
働き方で労働時間を増やしてゆくとしても、いつしか限界はある。そうなると、次の改善機会は仕事の質だ。ある程度以上忙しい人は皆この段階まで進んでゆくことになる。そうなってくると、労働時間の多い少ないと比較すること自体、あまり意味がなくなってくる。勿論、長時間労働に耐える体力がある方がいろいろな意味で自由度が大きいのは事実だけれども、それは仕事の能力を決める様々な要素の一つに過ぎない。
最後に一つ。今回の分析で面白かったのは、自分の認識とデータが異なっていたことだ。私は自分が週80時間以上働いていたと思っていて、そういう話を他の人にして驚かれたりしていた。でも、実際にデータを見ていると、労働時間の多かった最初2年でも週平均で70時間程度。月にして40時間ものズレがある。多分、忙しい時期は強く記憶に残っているし、たくさん働いた話は何となしに誇らしいこともあり、こういうバイアスが生じたのかもしれない。
改めて、データに基づく議論が重要だということを痛感した次第であります。